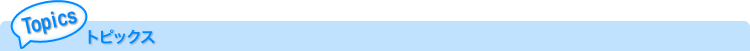自然に学ぶ研究事例
| 第34回 最終回 | 維管束植物に学ぶ材料開発 |

らせん状繊維の束で、すべて左巻き。植物の種類によって、直径数ミクロンから数百ミクロンのものが採取できる。写真は、ハスから採取したらせん紋(上)と、それに銀(左下)およびニッケル-リン(右下)の無電解メッキを施したもの。ハスの茎を折ると微細な白い糸をひくが、それがらせん紋である。
植物の導管と師管は、養分や水を運ぶ生命線です。その周囲にある形成層を合わせた3組織を維管束と呼びますが、コケ類、藻類、菌類以外のすべての植物に存在するものです。そして、導管の周りには、らせんや輪っか状の2次細胞壁が形成されることが知られています。植物の種類によって異なりますが、らせん構造は直径が数ミクロン〜数十ミクロン、長さは数ミリ〜数十センチに及び、すべて左巻きの丈夫なセルロース繊維なのです。それを鋳型にして電子材料をつくろうという、ユニークな研究があります。
高周波やマイクロ波などの電磁波は、さまざまな分野で利用されていますが、携帯電話、衛星放送など、大量の情報を早く送るために、高い周波数帯の利用が拡大しています。携帯電話では現在、800メガヘルツ帯と1.5ギガヘルツ帯がおもに使われており、たとえば1ギガの場合、なんと1秒間に波が10億回も往復しているのです。光、立体テレビなどになると、さらにギガの1000倍というテラの世界へ入っていきます。
電波を受発信するアンテナは、周波数が高くなるにつれて短くなります。当然、電子回路も小さくなり、それに使うコイルも超小型化が求められますが、現在の精密加工技術では直径50ミクロン程度が限界だと言われています。そこで、植物がつくる直径数ミクロンのらせん状繊維(らせん紋)を、そのままコイルとして利用できないかと考えたのです。天然の材料をそのまま使うことができれば、生産過程における環境負荷の低減にもつながります。
これまでの研究では、いろいろな植物から、らせん紋を取りだして銀やニッケル-リンなどのメッキを施し、電気を通すマイクロコイルがつくられました。そして、このコイル特性(インダクタンス)を評価したところ、ギガヘルツ帯の高周波に作用するという結果も得られました。作製するプロセスがユニークなだけでなく、電子素子としての可能性は高く評価されており、植物コイルを使った電子回路が、微小アンテナや電磁波吸収材料として普及する日が、そう遠くない未来にやってくるかもしれません。このような研究助成や異分野の方からの評価を励みに、植物コイルの展開研究に本気で取り組んでいます。
 |
彌田(いよだ) 智一 教授 東京工業大学 資源化学研究所 自分の考えを信じ、研究を突き進める |