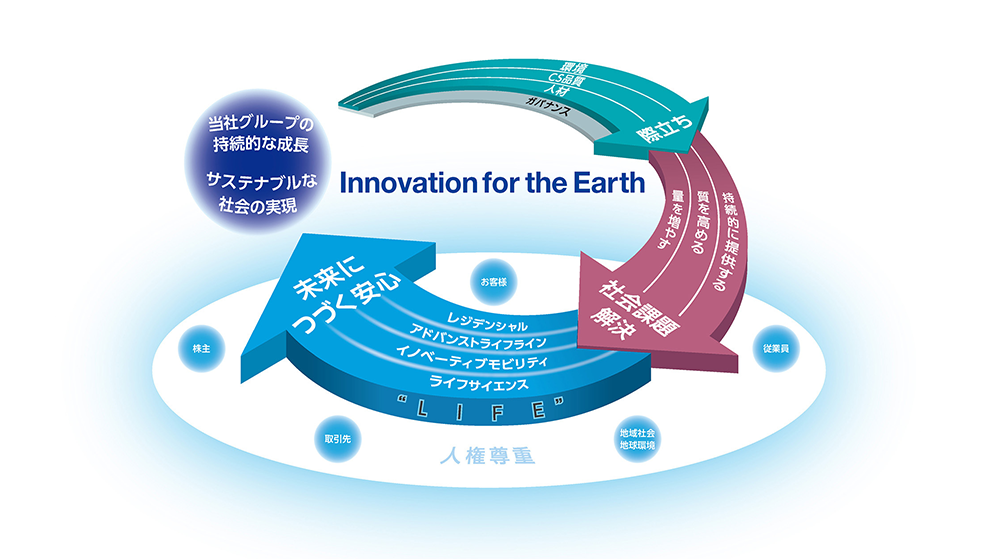
更新情報
-
- 2025年3月31日
- 日本政策投資銀行の「DBJ環境格付」で最高ランクを取得
-
- 2025年2月13日
- S&P Global社サステナビリティ格付け「S&P Global Sustainability Yearbook 2025」で上位10%企業に選定
-
- 2025年2月7日
- CDP「気候変動」および「水セキュリティ」分野の情報開示においてAスコア、「フォレスト」分野でA-スコアを獲得
-
- 2024年12月24日
- ESG投資指標「Dow Jones Sustainability World Index」の構成銘柄に13年連続で選定
-
- 2024年12月1日
- 積水化学グループ カスタマーハラスメントに対する基本方針を制定しました。
PDFダウンロード
積水化学グループのサステナビリティに関する各種データをPDFで掲載しております。

