社外取締役 × 人事担当取締役 対談(2025)
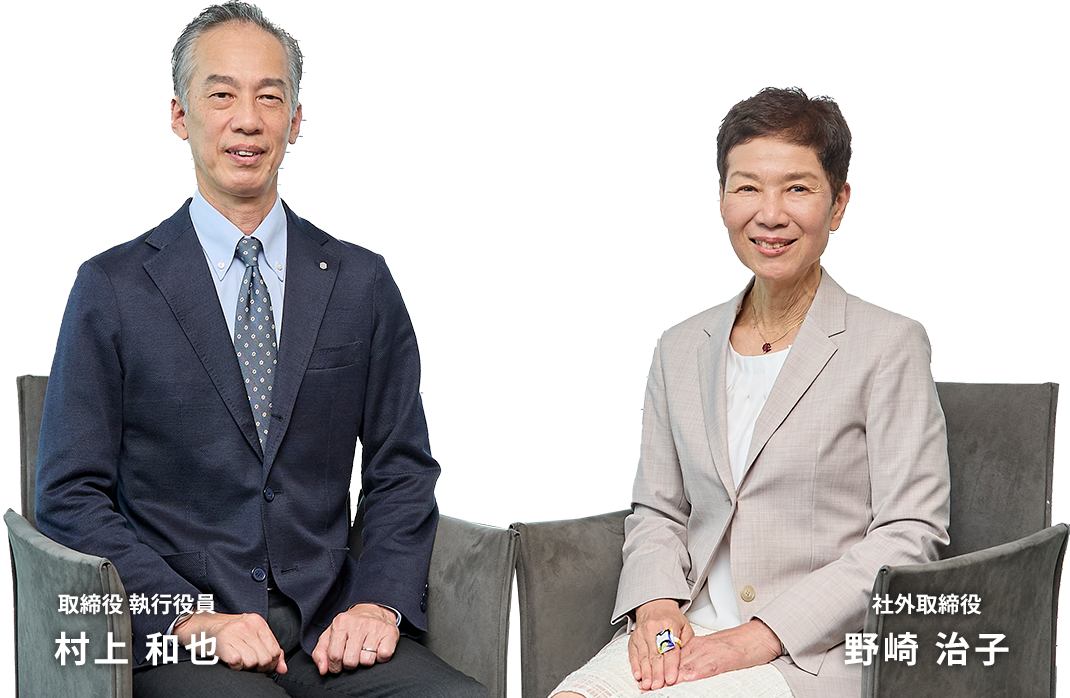

社外取締役 × 人事担当取締役 対談
積水化学グループでは、マテリアリティの1つに「人的資本」を掲げ、「全従業員が挑戦したくなる活力ある会社」であり続けることが大切だと考えています。
そのための取り組みと経営戦略との関係について、社外取締役としてダイバーシティ推進委員会の委員長を務める野崎取締役と、人事部長を務める村上取締役が、対談を実施しました。
その内容をご紹介します。

人的資本に対する現在の取り組みと、それに対する評価、手応えをお聞かせください。
村上当社では「従業員は社会からお預かりした貴重な財産」という人材理念を掲げており、社員の成長のために資源を投じる姿勢はこれまで一貫して変わっていません。ここ数年は、経営戦略と連動した人事制度の整備に注力すると共に、人的資本への取り組みを可視化し社内外に発信することを強く意識しています。さらに、展開施策の有効性を検証するため、経営指標に結びついているかを確認する生産性指標の導入にも取り組んでいます。
野崎製品を通じてイノベーションを生み出してこられたのと同様に、人材戦略においても先駆的な取り組みをしていると感じています。中期経営計画で人的資本に3年間で120億円を投資すると明示したことも、経営者の覚悟の表れとして高く評価しています。現在働いている人にとって「自己の成長」は大きなキーワードとなっており、自分にどんな力があり会社がどんな力を求めているのか、双方を可視化しマッチングさせることは、これからの人事にとって極めて重要です。多様な事業を展開する企業として、各カンパニーとの兼ね合いも緻密にかつ丁寧に可視化して、それぞれの事業の特徴が生きるように制度設計されている点は大変素晴らしいと思います。
村上今後もカンパニーとコーポレートが連動しながら、中長期的な視点での人事戦略を策定、実行していきたいと思います。
野崎コーポレートがグリップをきかせる領域は、カンパニーのサクセッションプランに関与し、カンパニーを超えた適所適材を進めることだと思います。いずれにせよ慎重でありながら当社にふさわしい在り方を果敢に模索していく姿勢は、まさに企業文化の象徴だと感じています。
挑戦行動の発現度、エンゲージメントに関して、どう評価していますか?
村上「挑戦行動の発現度」は、現在当社グループの人的資本の重点KPIとなっており、社長自らも従業員一人ひとりの挑戦を後押しする発信を続けています。直近の実績である56%という数値は大きく上昇していますが、この数値にまだ満足はしていません。挑戦に対する評価は適切なのか、従業員が成長実感を得られているかといった点において、さらなる工夫や対策が必要だと強く感じています。
野崎挑戦行動の発現度もエンゲージメントスコアも、海外の方が高く出やすい傾向があります。日本はおそらく謙虚さやもっとよくできるという向上心からスコアが低く出がちなので、絶対値として見るよりスコアの変化を見ることが大切です。さらにいえば、激化するグローバル市場で戦うには、ときには「私は挑戦している」「だから○○してほしい」と言い切るメンタリティを養うこともこれからの課題です。
村上さらに、数値が上昇トレンドにある今こそ重要な局面です。たとえば「頑張って挑戦したけど、ちゃんと評価されているの?」というような状況に、どう対策を打てるか。ここからが本当の勝負だと考えています。
野崎挑戦行動の理解を深める場のひとつとして「トップと語ろう」という企画が提案されていて、社員が働き方やイノベーションについて役員と直接話し合う場となっています。私も何度か参加させてもらってい るのですが、そこで感じるのは、社員の皆さんが忖度なく発言し、社長をはじめ役員も本音で応えているということです。トップ自らが失敗を歓迎し、挑戦を後押しする姿勢が印象的で、社員の皆さんの信頼感やエンゲージメント向上につながっているように思います。
ダイバーシティ推進委員会の取り組み状況と、取締役会直結の意義を教えてください。
野崎私はダイバーシティ推進委員会の委員長を務めていますが、社外取締役全員が委員会メンバーとなっており、毎回活発な議論と提言が行われています。たとえば、「女性の採用比率の目標値をさらに上げましょう」という提案や、「キャリア採用でも女性の歓迎を強く打ち出してみてはどうか」「幹部候補社員育成のために、グループ会社役員のポジションをさらに活用してはどうか」といった意見も出ています。実際に施策として実現しているものも多く、委員会は有効に機能していると感じています。取締役会の諮問機関として位置付けられている事例は、国内でも珍しいのではないでしょうか。
村上社外取締役の皆さんの経験や知見を執行側がしっかりと受け止め、執行側の意思と責任のもとに実行していくべきだという考えから、諮問委員会という形式をとっています。実際に、野崎さんをはじめ皆さ んから、人材や組織に関する多くの問いかけや提言をいただいています。
野崎執行側ではないからこそ言えるのですが、施策の実現にはもう少しスピード感があってもいいかなとも感じています。
村上耳が痛いところです。人事部門としてはスピード感をもって改革しているつもりでも、それを上回るご指摘をたくさんいただき、大変良い刺激になっています。
野崎単に女性の比率を上げるといった表層的な取り組みだけでなく、D(Diversity)、E(Equity)、I(Inclusion)、B(Belonging)までを一体としてとらえて議論しています。最終的にはエンゲージメントと同じ 意味で、Belonging、つまり当社グループの一員であることを誇りに思い、違いを強みに自分らしく活躍できること、結果として個人と会社の成長につながることが最終的に目指すダイバーシティだと考えています。
「多様な人材の活躍」を実現するため、今後具体的にどのような取り組みを考えていますか。
村上現在、女性の採用比率は約30%、新任管理職比率は約10%、そして全管理職に占める女性の比率はようやく5%と、数値目標に対してはまだまだ比率を上げていく必要があります。ただ、本来的な目的は数値目標そのものではなく、様々なスタイルの働き方を認めるなど職場環境を整備して、自分らしく活躍してもらうことであり、それがひいては企業の成長にも結び付いていくことです。例えば、新たな試みとして女性管理職のメンター制度を進めています。女性管理職の上司の大半は男性で、歩んできたキャリアも異なりますから、これまでの通常のラインでは共有されなかった悩みが多数出てきています。こうした取り組みを通じて、当事者の実感とのギャップを埋めるための着目点や改善点が見えてくるなど、一定の効果を実感しています。また、職場環境を改善すれば、親の介護などの事情を抱えるシニア層の活躍の場も広がると考えています。まだまだ改善できるポイントは多くあると思っています。
野崎おっしゃる通りです。「多様な人材の活躍」というと、「女性管理職」ということが注目されがちですが、本来は性別などの外的ダイバーシティを超えて、内的ダイバーシティも含めた広義の多様性を実現していく必要があります。最初は女性の採用比率や管理職比率を上げるところから始めるとしても、年齢、国籍、職種や組織にとらわれない幅広い多様性が実現されることで、業績やイノベーションにもつながっていくと思っています。
人材不足の中で、当社の人材ポートフォリオをどう評価し、どのような層に着目すべきと考えますか。
野崎イノベーションを起こしていくには、0から1を生み出す人だけでなく、1から10を築く人、10を100に、さらに1,000に拡大していく人材が必要になってきます。さらに当社は製造業ですから、より細かなプロセスやスキルが存在しています。次期中期計画に向けては、将来必要となる工数やスキルの過不足を可視化して、前後左右にミッションや可能性を広げる機会を設けることで、中期計画の目指す戦略ポートフォリオに適合した人材ポートフォリオが出来上がっていくことを期待しています。一方で、人手不足は今後さらに深刻化するのは明らかですから、外国人材、シニア人材やハンディキャップのある方にどれだけ力を発揮いただけるのか。当社がそこで知恵を絞り、パイオニア的な存在になれたらいいなと思います。
村上採用面では、野崎さんから「新卒採用にどこまで依存するのか」というご指摘をいただいたこともあります。現在グループ全体で年間1,000人を超える人材を採用しており、その半数強が新卒ですが、目標人数を確保するのに毎年苦労しているのが実態です。採用活動として母集団形成から選考、内定者フォローまで、採用チームは大きなエネルギーを投入しています。当社が求める人材像や、採用市場の変化に合わせて、より柔軟に即応できる採用モデルへの転換が必要な時期に来ていると考えます。
野崎アカデミアの立場から申し上げると、企業においてこんなに面白い仕事、社会に役立つ仕事ができるとアピールしていただき、博士号をもつ人材の採用やインターンシップも積極的に展開していただきたいですね。
DX・ESG・グローバル人材の獲得・育成についての取り組み、評価を聞かせてください。

村上現在当社グループの海外売上比率は約30%で、今後さらなる拡大を想定しているため、グローバル人材の育成は急務です。グローバルの組織運営においては、これまでは日本からの駐在員がマネジメントを担うケースが主流でしたが、次期中期計画ではグループ人材全体の中からの適所適材を強く打ち出す計画です。それぞれの海外現法での後継者育成をこれまで以上に促進し、将来的には多数の現地人材に海外現法の経営を委ねたいと考えています。またESG人材については、「ESGの専門家」としてではなく、自社の事業の意義や社会インパクトを正しく理解し説明できる経営人材を育てることに注力していきます。
野崎海外現地法人では、トップになるためのマルチなキャリアパスの例示は必須です。本社役員も対象です。ESG人材は、その役割に誇りをもてるような動機付けができると良いですね。社内の評価というよりは、業界や学会で第一人者として評価を受ける等、専門性の評価がモチベーションにつながると思うので、そうした魅力をうまく伝えていくことが大切だと感じます。
村上一方、DXについてはとにかくスピードが求められます。即戦力となる外部人材の獲得に向けては、専門職としての処遇をより充実させようと動いています。ただし現実的には、こうしたプロ人材の採用は難しく、DX人材の社内育成が鍵になると考えており、社内人材のリスキリングを積極的に進めています。
野崎経営戦略と人材戦略の整合性が見てとれ、採用、登用、育成が一体となって体制整備が進んでいることを高く評価しています。
取締役会の意思決定プロセスと実効性について、どのように見ていますか。
野崎議題に関する情報は背景を含めた詳細な経緯まで丁寧に共有されており、社外取締役として安心して発信できる環境が用意されています。生産工場や研究所を視察して社員の熱意や課題意識を知るなど当社を立体的にみる機会が設けられています。また社外取締役同士も、形式的なやり取りにとどまらず率直な意見交換や問いかけができる関係性が築かれており、議論の質も以前より高まっていると感じています。一方で、社外取締役からの質疑に終始する場面が多いのが実情で、取締役会の場においても、もう少しカンパニー間の議論にも時間を使ってもらいたいと思っています。シビアで無駄がないのは素晴らしいと思いますが、お互いの取り組みを認め合って褒め合うなど、もう少し遊びがあってもいいかもしれません。
取締役会の多様性をどう評価し、今後どのように高めていくべきと考えますか。
野崎男女共にキャリアに多様性があり、監査役は専門的見地から話をされ、多様性は十分に確保されています。当社の常識は、必ずしも社会の常識ではありません。常識は時代と共に変わりますし、異なる経験や立場、時代の変化への感度が大切にされていると思います。欲を言えば、今の社外取締役の平均年齢は高くなっているので、若い世代が増えるとうれしいです。これから先の10年を見てこの重要な役割を果たしていくとなると、より若い世代の見方が大事になってくると考えます。

人事トップである村上取締役にとっての「挑戦」について聞かせてください。
村上私の挑戦は、社員の挑戦を見える化し、納得感のある評価制度までを定着させることです。掛け声だけの「社長が言っているから」「上司が言っているから」仕方なくやる、では意味がありません。上司と部下 が現実に即した納得できる挑戦を設定し、実行し、適切に評価する仕組みをつくり、挑戦し続けることを促す空気、企業文化を根付かせることが私自身の挑戦だと考えています。
社外取締役の立場として、投資家の皆さんには当社のどこに期待してほしいと考えますか。
野崎当社は、卓越した技術力と多様な市場を結ぶ強固なサプライチェーンを有しています。確実に「稼ぐ力」は、まさに複数のビジネスを有する企業ならではの強みです。加えて、経営陣は明るく本質を見抜く目利き力を備えており、社員も社会課題の解決に誇りと責任感をもって挑戦しています。こうした人材の力は企業価値の源泉であると考えます。また、「3S精神(Service、Speed、Superiority)」に象徴される企業文化と、時代に合わせて柔軟にビジネスポートフォリオ変革する力も、不透明な時代における競争力の鍵です。財務指標に表れにくい、人的資本や文化のもつ力に着目いただき、積水化学グループの長期的な成長に期待していただきたいと思います。