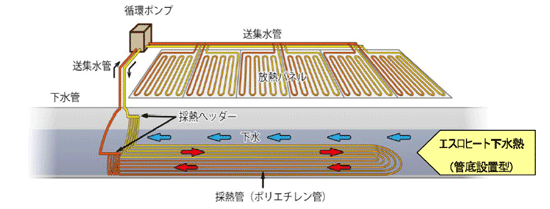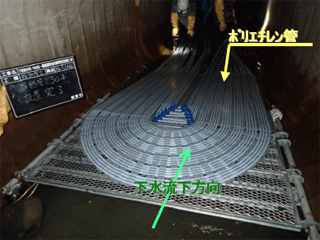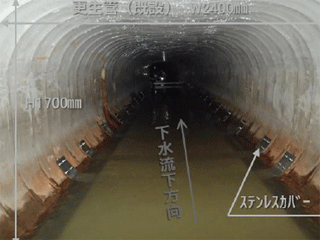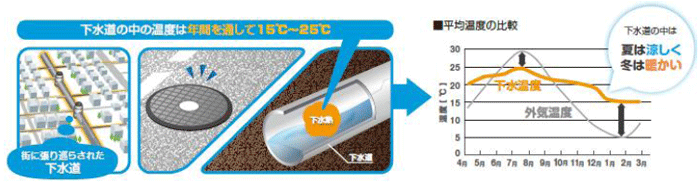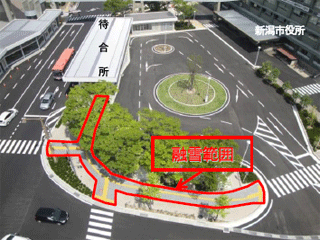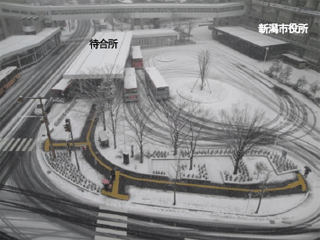積水化学工業株式会社(代表取締役社長:髙下貞二)の環境・ライフラインカンパニー(プレジデント:久保肇)が手がける未利用エネルギー活用システム「エスロヒート下水熱(管底設置型)」が、新潟市が実施した道路融雪設備工事に採用され、その効果が検証されましたので、お知らせします。本事例は、2014年11月に発売した同製品の初めての採用事例です。
1.背景
新潟市では、2013年より「環境モデル都市」として低炭素型都市づくりが進められており、自家用車から公共交通機関へのシフトが推進されています。
|
そこで、 |
(1)新たな交通システムBRT(Bus Rapid Transit)の導入 |
|
|
(2)交通結節点の整備 |
新潟市は降雪量は少ないものの、気温が低いため雪が溶けずに残り、通勤や通学の支障となるケースが多くありました。こうしたことから、公共交通機関の利便性向上には、融雪された歩道の確保が課題となっていました。
2.融雪設備工事の概要
|
|
|
|
〔下水熱融雪システムのイメージ図〕 (以下、工事に関する図、写真はすべて(株)興和より提供)
|
|
この融雪システムは、バスターミナルの地下に埋設されている更生後の合流管(2400mm×1700mm)の管底部約100mにわたって設置された採熱管と、歩道表面部に設置する放熱パネルで構成され、これらが接続されています。採熱管で下水から回収した熱を熱媒体である循環液に移し、それを放熱パネルに送ることで歩道に積もった雪を溶かすシステムです。
また、本システムはヒートポンプを介した加温・冷却を行わずに、下水から得られた熱のみで融雪するとても経済的なシステムとなっています。
〔融雪設備(採熱部:エスロヒート下水熱)の設備構造〕
|
採熱管折返し部(着底前) |
管底設置部分(施工後) |
|
|
|
3.融雪システムの有効性検証について
下水温度は外気と比べ、年間を通じて15℃~25℃と安定しており、冬は暖かく、夏は冷たいという特性があります。この下水と気温との差(熱エネルギー)を冷暖房や融雪等に利用することにより節電効果が発揮されます。
|
|
新潟市における本システムは、下水の持つ熱特性を利用した融雪設備としての効果の実証を行いました。
冬季の運転により、エスロヒート下水熱による融雪システムの敷設整備されている歩道部分だけが融雪されていることが確認できました。
【冬期融雪試験結果】 <2016年1月>
|
〔融雪システム整備場所(全景)〕 |
|
|
|
|
|
融雪システム整備場所(全景) <2015年7月27日撮影> |
融雪状況(全景)<2016年1月12日撮影> |
|
|
|
|
〔システム敷設部分の様子(歩道部)〕 |
|
|
|
|
|
融雪システム整備場所(歩道部竣工時) |
融雪状況(歩道部)<2016年1月12日撮影> |
4.「エスロヒート下水熱」について
我が国における下水熱利用は、近年、管路内における熱回収技術が確立されたことから、管路内への民間事業者の熱交換器設置を認める規制緩和が行われるなど、活用が進められている技術です。当社においても、2012年度に国土交通省の下水道革新的技術実証事業(B-DASH)において、大阪市、東亜グラウト工業株式会社と実証実験を実施したほか、2013年度には仙台市との共同研究により、「エスロヒート下水熱(らせん型)」を用い、実管路で下水熱を回収し、民間商業施設での給湯利用を進めています。
|
|
5.融雪技術が平成28年度B-DASH予備調査事業に採択
また、本件とは別に、融雪技術に関して、国土交通省の平成28年度B-DASH予備調査事業「下水熱を利用した道路融雪技術の調査研究事業」に、(株)興和を代表者とした新潟市と弊社の3者共同体で応募し、4月5日に採択が決定しました。本事業では、下水熱で温められた循環水をポンプで融雪パネルに送るシステムを用い、高熱伝導材を使用した場合の車道融雪への適用条件をシミュレーションで確認するほか、管理者が異なる道路と下水の連携体制等の整理を行う予定としています。
当社では引き続き未利用エネルギー活用システム「エスロヒート下水熱」を通じて、環境に優しいまちづくりに貢献していきます。
以上